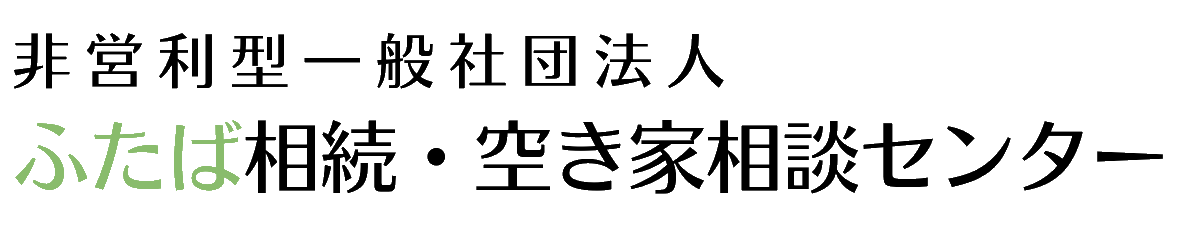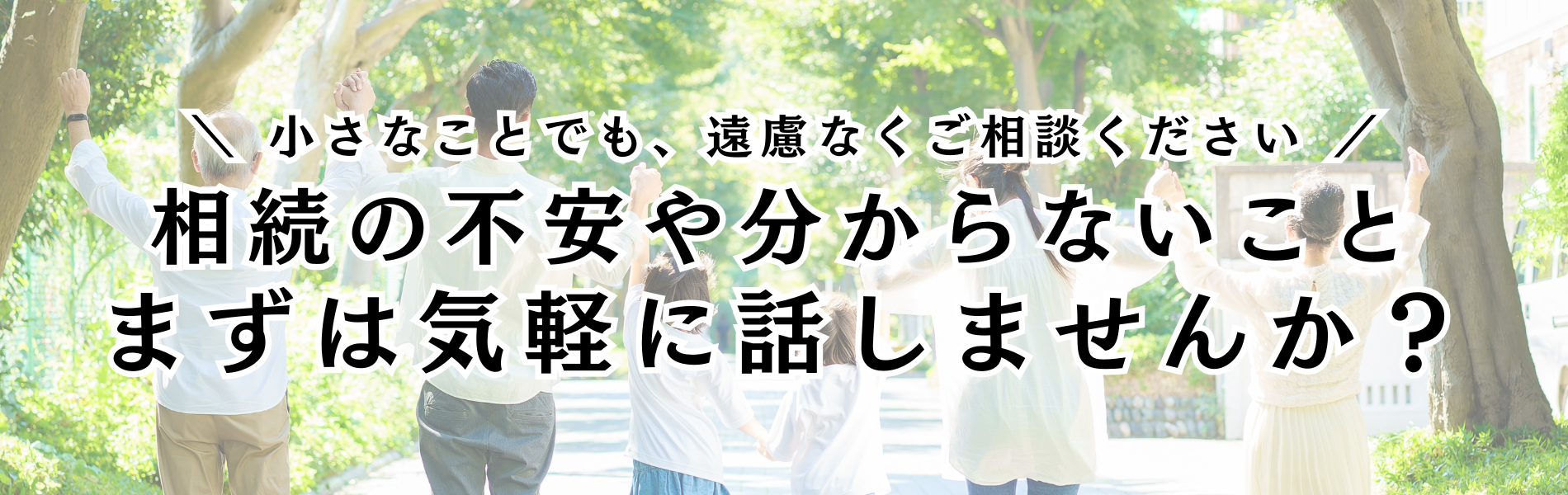こんにちは。
「相続で土地をもらったけど、正直いらない…」
そんなお悩み、ありませんか?
・遠くて使い道がない
・固定資産税だけ払っている
・売りたいけれど、不動産屋に断られた
・草刈りや管理が大変…
そんなときに検討できるのが、「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。今回は、制度の内容や使い方、注意点まで、やさしく紹介します。
相続土地国庫帰属制度ってどんな制度?
簡単に言うと、「相続などで取得した不要な土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる」制度です。
2023年4月にスタートしたばかりの新しい制度で、法務省が窓口になっています。放置された土地が増えると、災害時やまちづくりの妨げになることもあるのですが、そういった問題を減らすためにできた制度です。
誰でも使えるの?【対象になる人】
いいえ。「相続で土地を受け取った人」だけが使える制度なんです。
具体的には、以下のような方です。
• 相続や遺言(いごん)で土地をもらった人(=相続人など)
• もらった土地が自分名義になっている人
• 共有名義の土地なら、全員の同意があること
逆に、こんな場合は使えません。
• 自分で買った土地
• 親から生前贈与でもらった土地
• 会社名義の土地(法人は対象外)
どんな土地でも引き取ってくれるの?
いいえ。すべての土地が対象になるわけではありません。
次のような土地は、申請しても引き取ってもらえません。
引き取ってもらえない土地の例
• 建物や古い空き家が建っている土地
• 他人の権利(借地・抵当権など)がついている土地
• ゴミや埋設物がある土地
• 崖地など、管理にお金がかかる土地
• 境界がハッキリしていない土地
• 所有権でもめている土地
• 他人の土地を通らないと出入りできない土地
• 汚染されている土地(元工場跡地など)
つまり、「国が安心して引き取れる、きれいで管理しやすい土地」であることが条件なんです。
手続きはどう進むの?【申請の流れ】
大まかな流れはこちらです。
1.法務局へ相談(任意)
→ まずは「うちの土地、対象になる?」と確認
2.申請書類の提出(必要書類あり)
→ 書類と一緒に、土地の写真や境界図なども用意
3.審査・現地調査
→ 法務局の職員が実際に現地を確認することも
4.承認されたら、負担金を支払う
→ 国が土地を正式に引き取ってくれます!
いくらかかるの?【手数料と負担金】
手続きには、以下の費用がかかります。
| 内容 | 金額(目安) |
| 審査手数料 | 14,000円/1筆 |
| 負担金 | 原則20万円/1筆 |
※負担金は「10年間、国が管理するのに必要なお金」とされています。
また、土地が広かったり、市街地にあったりすると、負担金が高くなることもあります。(例:100㎡の宅地 → 約55万円のケースも)
注意点もチェック!
• 申請後でも、条件を満たしていないと不承認になります。
→ 建物が残っていた、境界があいまいだった…など。
• 手数料は返ってきません。
→ 申請を途中でやめても、審査に落ちても14,000円は戻りません。
• 承認後は30日以内に負担金を支払う必要があります。
→ 期限を過ぎると、せっかくの承認が無効になることも。
上手に使えば、土地の悩みが解決できるかも
「いらない土地があるけど、どうしていいか分からない」
「子どもに負担を残したくない」
そんな方にとって、相続土地国庫帰属制度は心強い制度です。
ただし、条件はちょっと厳しめなので、まずは法務局に相談してみるのがおすすめです!相談は無料で事前に土地の状況をチェックしてもらえますよ。
▶ 法務省の公式サイトはこちら