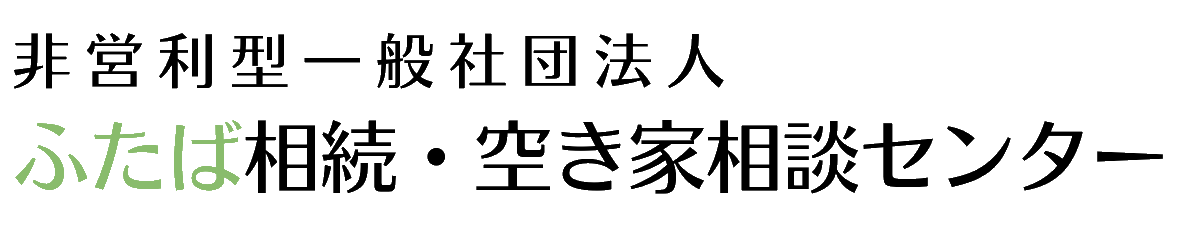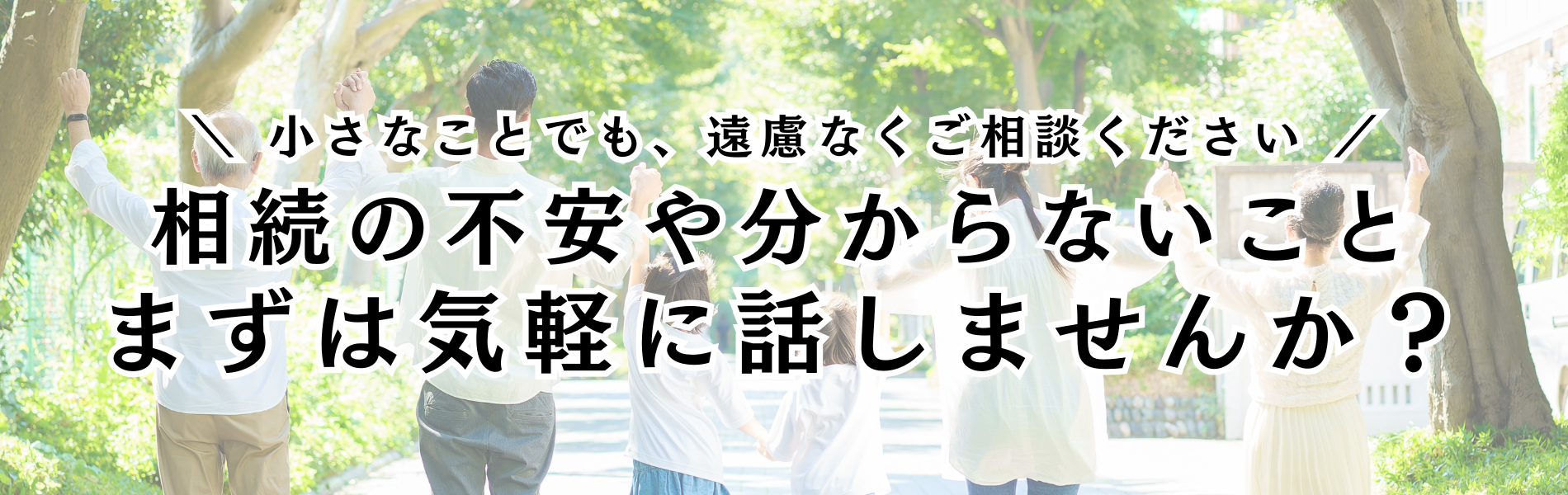こんにちは。
相続や不動産のご相談を受けていると、最近よく聞かれるのがこの質問。
相続した土地、国に返せる制度…
実際は難しいって聞くけどどうなんですか?
そう、今話題の相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)。不要な土地を国に引き取ってもらえる画期的な制度ですが、実は「思ったよりハードルが高い」「実際には使えない」といった声も多いんです。
今回は、この制度がなぜ“使いにくい”と言われるのか?
実際のデータや、報道・相談事例などをもとに、分かりやすく解説します。
※ この制度そのものについて知りたい方はこちらをご覧ください。
制度の利用件数は?【申請数 vs 実際に引き取られた数】
法務省によると、この制度が始まった2023年4月から2025年5月末までの実績は以下の通り。
• 申請件数:3,854件
• 国が引き取った件数(承認):1,699件
• 却下件数:58件
つまり現時点で約4割が国に引き取られていることになります。(審査中のものも多くあるため、実際の割合は現時点では不明です)
「思ったより使えているのでは?」
そう思うかもしれませんが、実はこれ、条件をクリアして、書類もちゃんと出せた人の中での話。途中で諦めたり、申請が却下・不承認になったりするケースも少なくありません。
実際「難しい」と言われる理由は?
1.要件がとにかく厳しい
「相続した土地ならなんでもOK」じゃないのがこの制度のポイント。法務省によると、次のような土地は引き取ってもらえません。
• 建物や物置がある
• 境界があいまい
• 他人の権利(地役権・担保権)がついている
• 崖地や大きな樹木、地下の埋設物がある
• 他人の土地を通らないとたどり着けない
つまり、「そのままでは手放せない土地」もたくさんあります。
境界をはっきりさせるために測量が必要だったり、建物や木の撤去が必要だったり…。申請前の準備だけでも、やらなければならないことが本当に多いです。
例えば、建物の撤去に数百万円、境界を確定させる測量に数十万円かかることもあります。しかもそれだけお金をかけても、申請が通らなかったら土地は引き取ってもらえません。
さらに、申請のために建物を壊したことで固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が跳ね上がってしまう…なんてことも。「そこまでのリスクを背負ってまで、やる価値があるのか?」と悩み、結局あきらめてしまう方も少なくありません。
「壊してまでやりたくないが、空き家は引き取ってほしい」
そんな方は、”ふたばの空き家募集”に応募するという方法もあります。
賃貸、媒体、買取、ご希望に合わせて対応いたします。
空き家を、あなたの希望と空き家に合った形で再生します!
2.手続きが想像以上に大変
手続きには、申請書のほかに、写真・境界図・位置図・印鑑証明書・地図などいろんな書類をそろえる必要があります。
また、法務局からの審査もけっこう細かく、
「杭の位置が分からない」
「写真が足りない」
「境界をもっと証明する資料を」
など、何度もやり取りが必要になることも。
申請してから半年〜1年以上かかることもあるため、「途中であきらめて取り下げた」ケースも多いのが現実です。
3.お金の負担も意外と大きい
この制度、いらない土地をタダで引き取ってもらえるわけではありません。実際には、こちらがお金を払って土地を手放す仕組みなんです。
まず申請時に必要なのは…
• 審査手数料:1筆あたり14,000円
→ この費用は申請と同時に支払います。
→ 不承認になっても、返金されません。
さらに承認されたら…
• 負担金(原則:1筆あたり20万円)
→ 土地の管理費用の“10年分”として、承認後に支払います。
→ 土地の面積や立地によっては、金額が増えることもあります。例えば、都市部の宅地(100㎡)で約55万円の負担金がかかった例もあります。
そして、申請の準備にもお金がかかる
申請書を出すまでに、状況によって以下のような出費が発生することも。
• 測量や境界確認の費用
• 建物・樹木・残置物などの撤去費
• 専門家(行政書士・司法書士など)への相談・書類作成サポート料
「土地を手放すために、こんなにお金がかかるなんて…」
そんなふうに驚かれる方も少なくありません。
制度の内容をよく知らずに申請を始めてしまうと、思わぬ出費や準備の大変さに戸惑ってしまうケースもあるので注意が必要です。
よくあるご相談・体験パターン
ちなみに、実際に寄せられる相談の中で「難しかった…」と感じたケースはこのようなものがあります。
•「建物を壊さないと申請できないと言われて、解体費が高くて断念」
• 「隣の土地との境界が不明で、測量に数十万円かかると知ってやめた」
• 「4筆まとめて申請したら、手数料だけで56,000円、さらに承認された後に負担金で80万円以上が必要になると分かり、負担が大きすぎて断念した」
• 「果樹や竹林もNGと聞いて、伐採を業者に頼むことになった」
このように、「制度があるのはありがたいけど、使うまでが大変…」という声がとても多いんです。
じゃあ、制度は使えないの?
いいえ、決してそうとは限りません。
制度の条件はたしかに厳しいですが、しっかりと要件を満たした土地については、実際に国が引き取っているケースも数多くあります。
たとえば、法務省が公表した2025年5月末時点のデータでは
• 申請件数:3,854件
• 承認件数:1,699件
• 却下件数:58件
• 不承認件数:55件
• 取下げ件数:628件
と公表されています。
この数字からもわかるように、却下や不承認よりも、承認された件数の方が圧倒的に多いのが現状です。
つまり、条件をクリアできれば「使える制度」なんです。ただし、その「条件をクリアすること自体」が、そう簡単ではないのもまた事実です。
制度を使うには“準備と確認”が大切!
相続土地国庫帰属制度は、「相続したけど使い道のない土地を手放したい」方にとっては、とても心強い制度です。
ですが、
• 申請できる人が限られている(相続・遺贈のみ)
• 土地の条件が厳しい
• 準備や費用がかかる
など、実際の利用にはハードルがあります。
こんな方は、まずは法務局へ相談を!
• 空き地や農地を相続したけど管理が大変
• 将来、子どもに迷惑をかけたくない
• 売れない土地があるけど処分したい
使えるかどうかは、まず話を聞いてみるのが一番です!